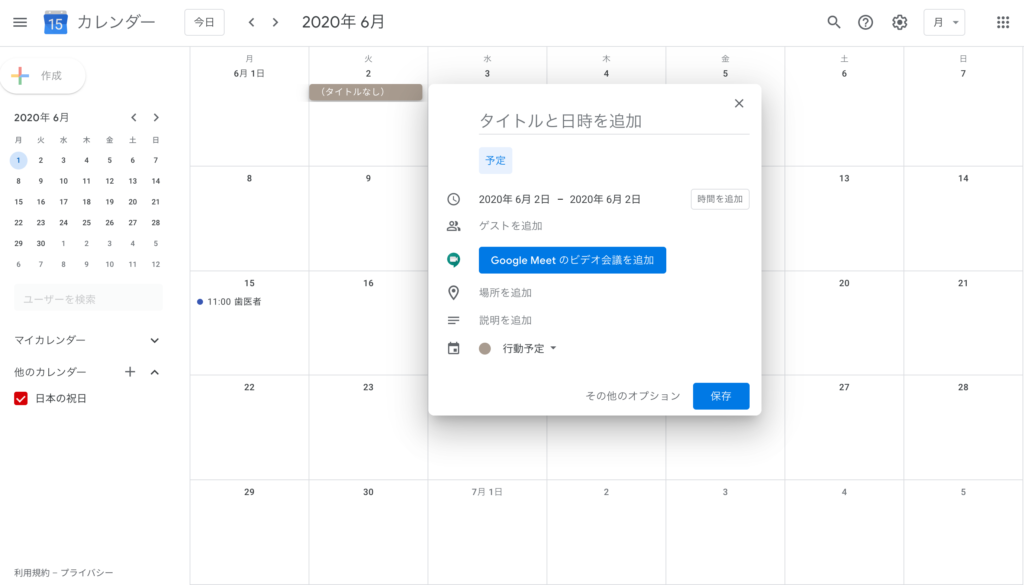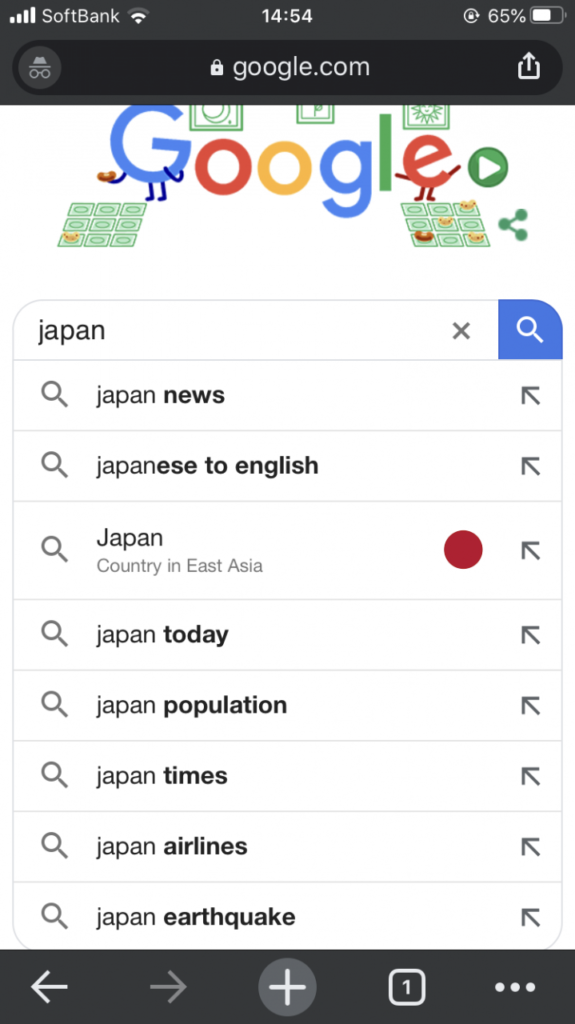お酒をやめたい会社員必見!飲み会でも「飲まない」を貫くための実践法とメリット
仕事後のストレス発散や、取引先や同僚とのコミュニケーションなど、社会人にとってお酒を飲む機会は多いものです。しかし最近では、健康面や体調管理の観点から「お酒をやめたい」「せめて飲む量を減らしたい」と考える会社員が増えています。
自宅での晩酌はやめられたけれど、飲み会に参加すると「気を使って紛らわせるため」に酒を手にしてしまう——。そんな方が意外と多いのではないでしょうか。そこで本記事では、飲み会のシーンでも上手に「飲まない」選択をするコツや、得られるメリットを詳しくご紹介します。
1. 飲み会でついお酒を口にしてしまう理由
1-1. 周囲の目や社内の人間関係を気にしてしまう
会社員の場合、上司や取引先、同僚との飲み会は業務の一環に近いこともあります。「お酒に付き合うのが当たり前」「断るのは失礼」といった空気が根強く、断りづらい雰囲気に負けてしまうケースが少なくありません。
1-2. 「手持ち無沙汰」や会話のきっかけに困る
「乾杯がビールだったからそのまま流れに乗ってしまった」「ソフトドリンクだと周りに話しかけるタイミングがつかみづらい」など、手持ち無沙汰を紛らわす手段としてお酒を選んでしまうことがよくあります。特に一息つきたいとき、アルコールでリラックスしようとする心理が働きがちです。
1-3. お酒を断る“理由づけ”が曖昧
「健康に気を遣いたいから」「最近は疲れやすいから」と漠然と断るよりも、明確な理由があると周囲に納得してもらいやすいものです。理由づけが曖昧だと、相手から「少しだけなら大丈夫じゃない?」と勧められ、断りきれなくなってしまうのです。
2. 飲み会でもお酒を飲まずにやり過ごすコツ
2-1. 最初の一杯からノンアルコールorソフトドリンクを注文
「とりあえずビール!」の流れに乗らず、最初の乾杯をノンアルコールビールやソフトドリンクにするだけで、後がとても楽になります。周囲にも「今日飲まないんだな」と伝わりやすく、無理な勧めを受けづらくなるでしょう。
2-2. はっきりとした“断り文句”を用意しておく
あらかじめ「内科で肝臓の数値を指摘されて、少し控えてます」「ダイエット中で医者に止められてるんです」など、相手が納得しやすい断り文句を用意しておくのがおすすめです。「薬を飲んでるからアルコールはNG」など、切実な理由を伝えるとさらに説得力が高まります。
2-3. “つまみ”や会話に集中して手持ち無沙汰を防ぐ
飲まない分、手や口が暇になるとお酒に意識が向きがちです。そんなときは、自分のペースで料理やおつまみを楽しんでみてください。また、同席者との会話にしっかり参加すると、自分が飲まなくても自然と時間が過ぎていきます。お茶やノンアルドリンクの種類を試すのも一案です。
2-4. 飲み会自体を工夫する
どうしても飲酒を断りきれない雰囲気の会であれば、店選びの段階から提案することも視野に入れましょう。ノンアルコールカクテルが充実している店や、料理が評判の店を選ぶことで「お酒を飲むだけ」の会ではなく、「食事や会話を楽しむ会」にシフトできます。
3. お酒を控える・やめることのメリット
3-1. 健康面の改善
アルコールを摂りすぎると肝臓への負担、生活習慣病のリスク、睡眠の質の低下など、さまざまなトラブルを招きます。お酒を控えることで内臓疲労が減り、朝の目覚めが良くなったり、仕事中の集中力が上がるなど多くの健康メリットが得られます。
3-2. 仕事のパフォーマンス向上
二日酔いや寝不足でパフォーマンスが低下しがちな方も、お酒を控えると翌日の頭がクリアに。会議やプレゼンで発揮できる力も高まり、結果的に社内での評価アップにもつながる可能性があります。
3-3. 金銭面のメリット
意外に見落とされがちですが、お酒を飲まないことで出費が減り、貯金や自己投資に回せるお金が増えます。毎回の飲み会で出る飲酒代は年間を通して計算すると大きな額になることも。浮いたお金でスキルアップの講座を受けたり、趣味に充てたりと、自分の将来に役立つ使い方ができます。
3-4. 体型・美容面での変化
会社員の多くはデスクワークで活動量が少なく、太りやすいと感じる方もいるでしょう。アルコールは糖質やカロリーが高いものが多いため、飲酒量を減らすことで体重管理がしやすくなります。さらに睡眠の質が向上すると肌の調子も良くなり、見た目の印象にもプラスに働きます。
4. 周囲の理解を得るためのコミュニケーション
4-1. 先に理由を共有しておく
職場の同僚や上司と事前に雑談の中で「最近は健康を意識してお酒を控えてる」などと軽く伝えておくと、飲み会の場で急に断るよりもスムーズに理解を得られます。「あの人は体調管理をしっかりしている人」という印象を与えれば、むしろ好感度が上がることも期待できます。
4-2. 「飲まなくても盛り上がれる」を証明する
職場での飲み会に参加する目的は「コミュニケーションを深める」こと。自分が飲まなくても、テンションを合わせたり、話題を盛り上げたりしていれば、周囲もお酒を強要しづらくなります。むしろ「この人と一緒なら、お酒がなくても楽しい」と思ってもらえれば成功です。
4-3. 飲みニケーション以外の場を提案
近年、飲み会だけがコミュニケーション手段ではありません。ランチミーティング、オンライン交流、週末のアクティビティなど、アルコール以外の場で関係を深める手段を提案するのも有効です。特にコロナ以降はオンライン飲み会やテレワークが普及し、仕事のスタイルも多様化しています。新しい交流方法を取り入れると、チームの絆も一層強まるでしょう。
5. 「飲まない」習慣を続けるコツ
5-1. 目標とする期間を設定する
最初から「一生飲まない」という目標はハードルが高いかもしれません。まずは「1か月飲まない」「週末のみノンアルで過ごす」など、具体的な短期目標を設定すると、モチベーションを保ちやすくなります。
5-2. 自分へのご褒美を考える
毎回飲み会をノンアルで乗り切ったときなど、小さな達成感を積み重ねるために自分へのご褒美を用意するのもひとつの手段です。浮いたお金でマッサージやスキンケア商品を買ったり、休日のプチ旅行を計画したりすることで、楽しく継続できます。
5-3. 同じ境遇の仲間をつくる
「お酒をやめたい」「控えたい」と感じている人は、実は周りに意外と多いもの。社内外問わず、同じ志向の人と情報交換すると、飲まなくても楽しめるお店やノンアルドリンクのレシピなど、役立つ情報が手に入ります。互いに励まし合うことでモチベーションも長く続くでしょう。
6. まとめ:無理せず「飲まない選択」を仕事と両立させよう
お酒をやめたいと思っても、「晩酌はやめれたけど、飲み会ではつい流されてしまう」と悩む会社員は多いです。しかし、最初から無理に完全禁酒を目指す必要はありません。最初の一杯をノンアルコールにする、理由を明確に伝える、周囲に先にアナウンスしておくなど、取り組みやすいポイントから実践していきましょう。
お酒を控えることで、健康面・美容面・仕事のパフォーマンスなど、多くのメリットを得られます。特に翌日の体調管理は仕事にも直結するため、社内評価が上がる可能性も高まります。「飲まなくても盛り上がれる人」という印象が定着すれば、周囲にも迷惑をかけず、むしろポジティブに捉えられることも珍しくありません。
ぜひ今回ご紹介したコツを参考に、無理なく“ノンアル習慣”を取り入れてみてください。毎日のコンディションが良くなり、気分も安定すると、仕事もプライベートもより充実するはず。あなたに合った「飲まないスタイル」を見つけて、健康的でストレスの少ない社会人ライフを送っていきましょう。